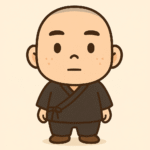「死」は本当に「終わり」なのか?

人が亡くなるということ。
それは肉体の機能が停止し、意思表示も、今まで通りの行動もできなくなることを意味します。
多くの人にとって、死は「すべての終わり」であり、そこには深い断絶と虚無感があるだけかもしれません。
私自身も、以前はそう感じていました。
しかし最近は、
もしかすると、私たちは死ぬことはないのではないか。
ふと、このような感覚を抱くようになりました。
命は形を変えてリレーされていく
たとえ肉体が滅びても、その人の記憶や知識、紡いだ言葉は、家族や友人、あるいはSNSを通じて見知らぬ誰かの中に残り、影響を与え続けます。
子どもがいれば、遺伝子という形でも命はリレーされています。
物質的な視点で見てもそうです。
私たちの体は燃え尽きれば骨となり、やがて土に還ります。
長い時間をかけて微生物に分解され、自然界の栄養素となる。
その栄養は植物を育て、他の生き物の血肉となり、いつか巡り巡って私たちの子孫の体の一部になるかもしれません。
そう考えると、死とは「消失」ではなく、大いなる自然のサイクルの中へ還っていく「循環」の一過程に過ぎないのではないか。
般若心経が説く「不生不滅(生じることもなく、滅することもない)」とは、まさにこの、形を変えながら永遠に続いていく命のあり方を指しているのかもしれません。
「断絶」と「つながり」の狭間で
しかし、頭ではそう理解しようとしても、現実の別れはまた別の顔を持っています。
あるお葬式で、喪主様がこう挨拶されました。
「母とはもう話すこともできませんが、どこか今でも私の隣にいてくれる感覚があります」
この言葉を聞いた時、ハッとさせられました。
果たして、大切な人を亡くした時に、この温かい感覚を持てる人が現代にどれだけいるでしょうか。
おそらく半数もいないのではないかと思います。
以前、90歳を超えた親御さんを亡くされた方が、「どうしても死を受け入れられない」と話しておられるのを目にしたことがあります。
世間から見れば「大往生」と言われる年齢でも、ご家族にとっては「突然の理不尽な別れ」だったのです。
見えなくなった「死へのプロセス」
なぜ、私たちはこれほどまでに死を受け入れられないのでしょうか。
それは、医療や介護が発展し、私たちの生活から「老い」や「病」、そして「死」の匂いが遠ざけられてしまったからではないでしょうか。
かつてのように、自宅で少しずつ弱っていく親の背中を見守り、命が死に向かっていく変化を肌で感じる機会は失われつつあります。
プロセスが見えないまま、ある日突然、病院から「死」という結果だけを突きつけられる。
それでは、たとえ何歳であっても心の準備などできるはずがありません。
「還る場所」としての死
喪主様が感じた「隣にいてくれる感覚」と、多くの人が感じる「断絶の痛み」。
その違いは、私たちがどれだけ「死」を生活の一部として、自然な「還る場所」として感じられているかにある気がします。
死を「忌避すべき終わり」として恐れるのではなく、大きな命の循環への「帰還」として捉え直してみる。
そして、元気なうちから「命は形を変えて繋がっていくものだ」という感覚を大切にする。
そうすることで、いつか訪れる別れの時、悲しみの中にも「あたたかな絆」を見つけられるようになるのかもしれません。