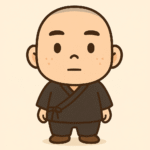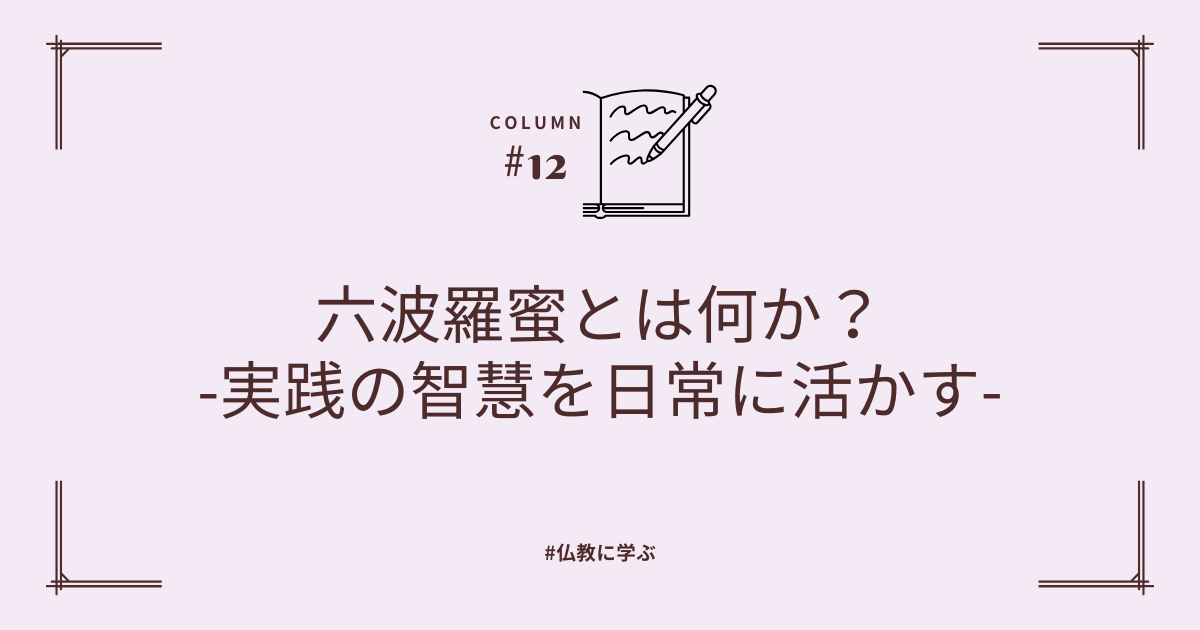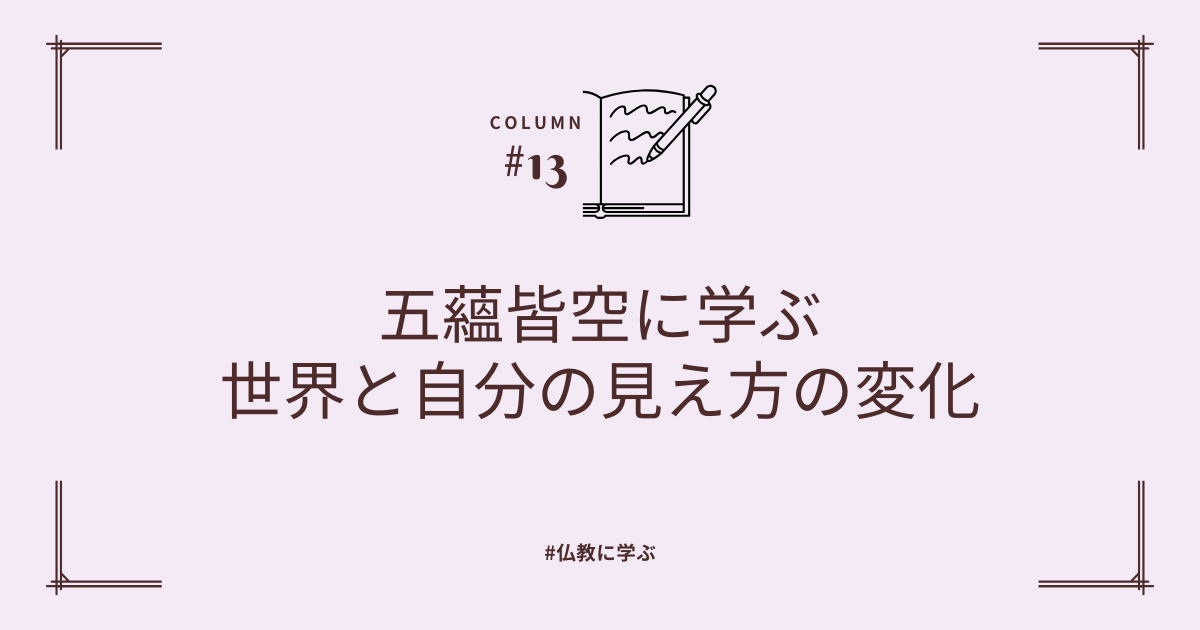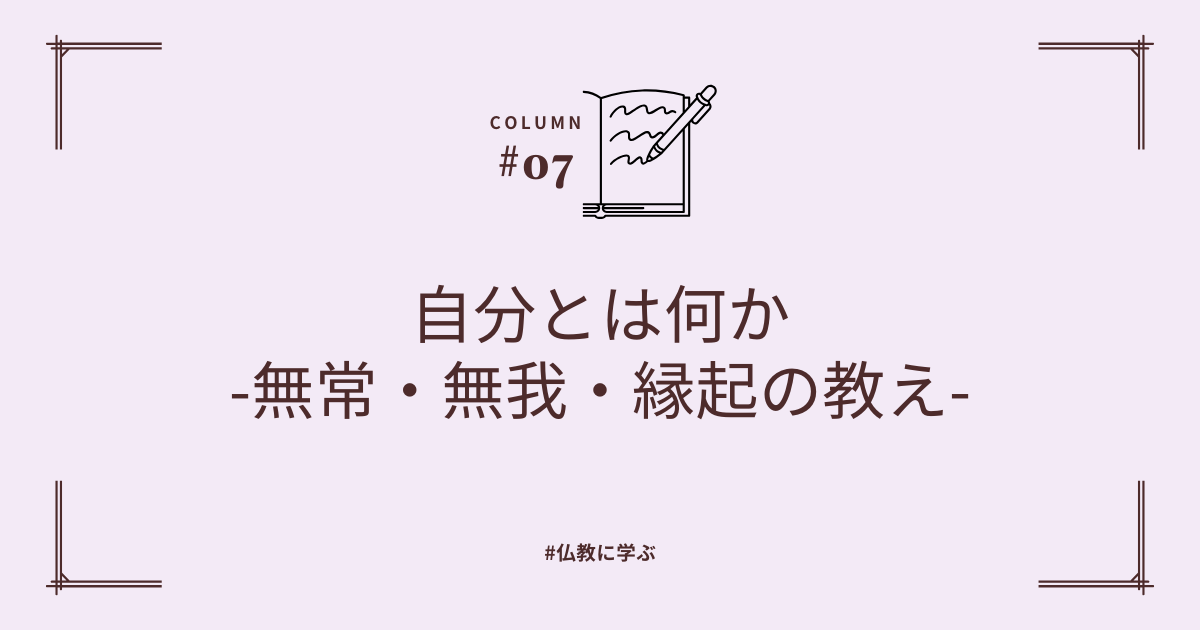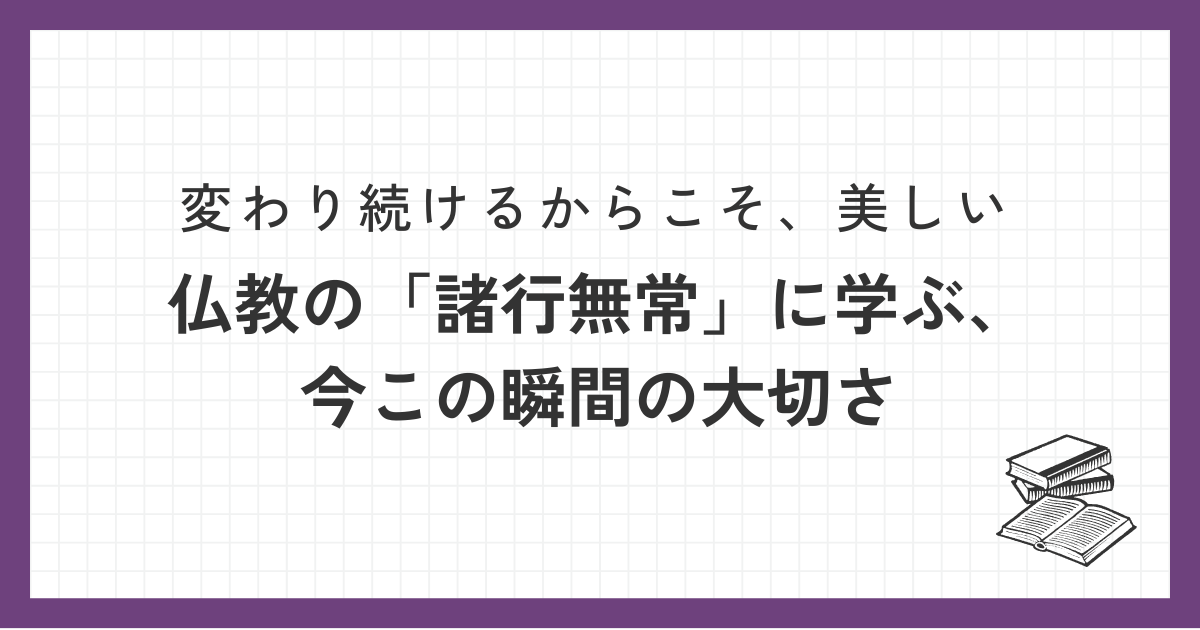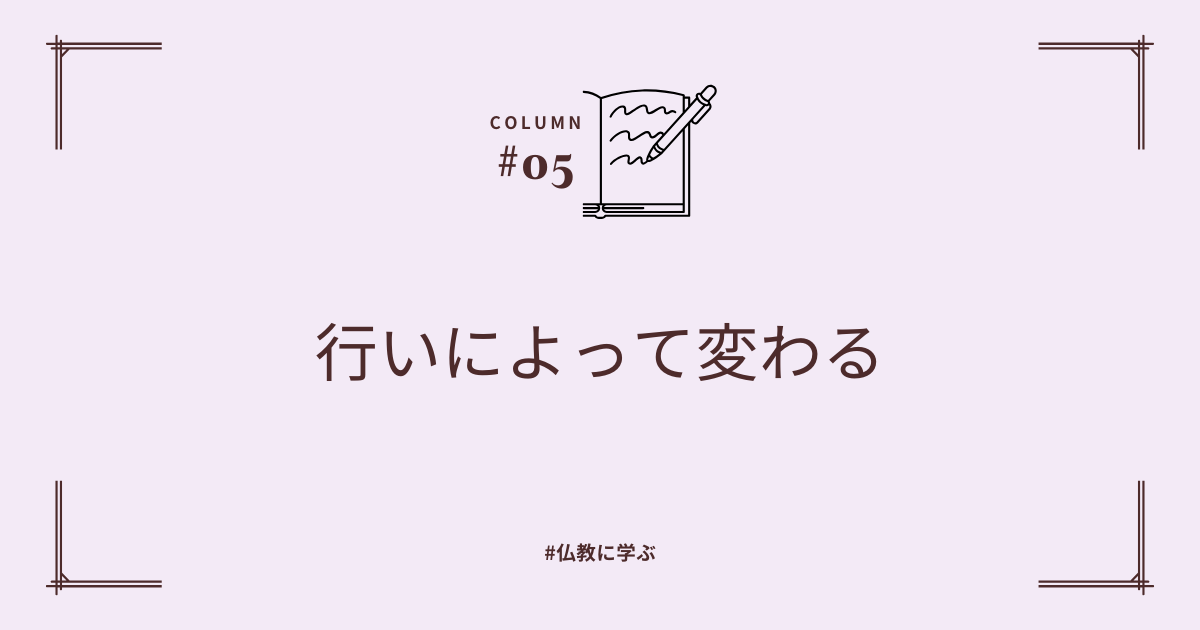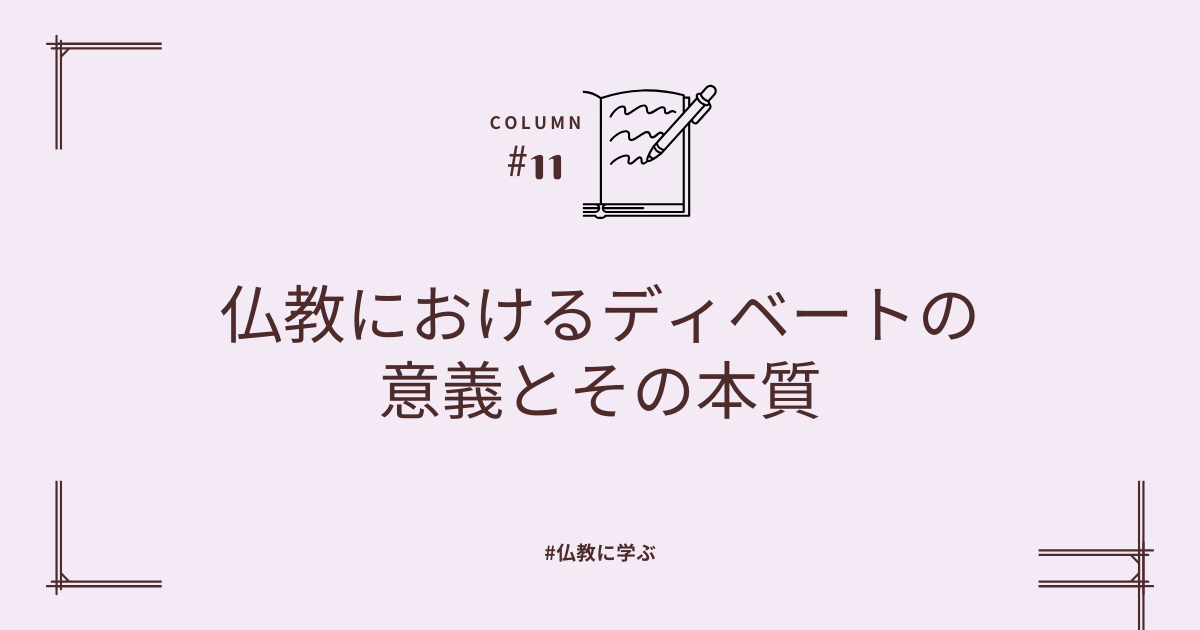本体なるものは存在しない
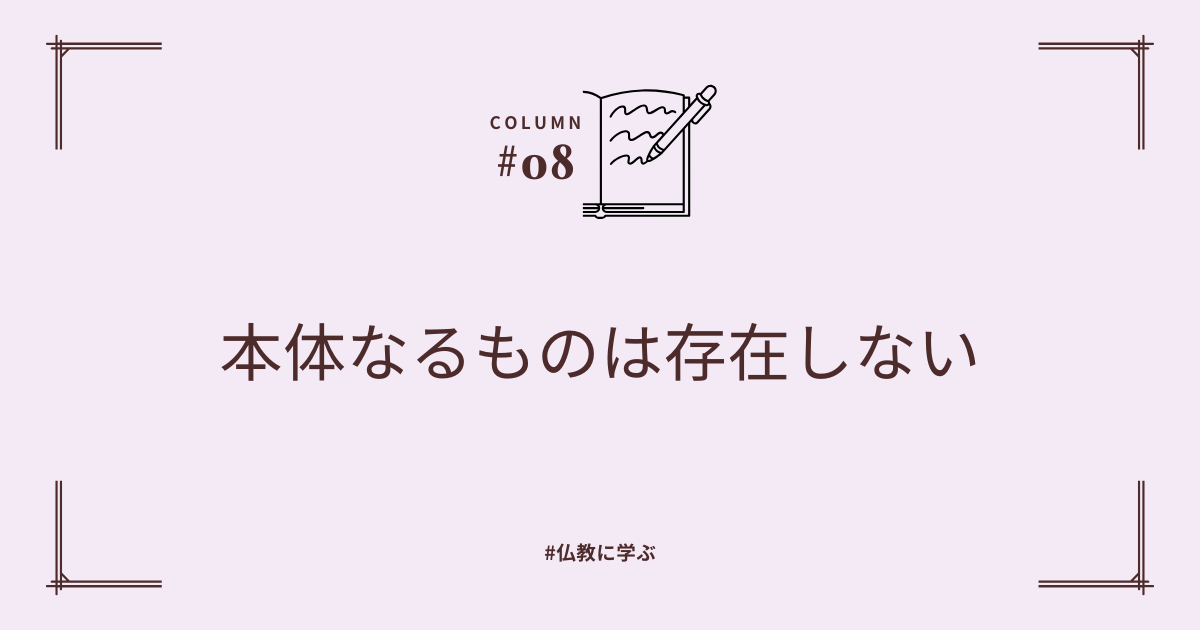
前回、「自分とは何か」という問いに向き合い、固定された実体は存在しないという仏教の無常・無我・縁起の教えについて考察しました。
今回はその続編として、書籍に沿って学んでいきたいと思います。
固定された実体は幻想に過ぎない
私自身、幼い頃から、「自分」というものが世の中に存在していると思っていました。
しかし、仏教の教えは、私たちの「自分」が、実は身体、感受、認識、形成、意識という五蘊の集合体であり、これらは常に変化し続けるため、固定された実体など存在しないと説きます。
一見、分かるようで分からないこの真理は、私たちが物事を感じるときにおいて、周囲の状況や体調、気分といった条件に左右される感覚そのものに由来しています。
たとえば、井戸水の温度を感じるとき、実際の水自体の温度は一定であっても、季節やその時の体調によって「冷たく感じる」あるいは「温かく感じる」ということがあります。
このように、私たちが体験するすべては、条件によって変わり、絶対的な基準では測り知れないことが分かります。
さらに、私たちの「自分」という感覚は、家族、友人、職場、地域社会といった様々なご縁の中で、絶えず形を変えながら再構成されています。
日々の生活の中で、私たちは喜びも苦しみも感じます。
しかし、これらは固定されたものではなく、一時的で流動的な現象に過ぎません。
ずっと喜んでいることはなく、反対にずっと苦しんでいるということはなく、時間が経てば、さまざまな感情が繰り返しています。
固定された自己という幻想に囚われると、苦しみへの執着が強くなり、心が重く閉ざされがちです。
しかし、苦しみもまた一時的なものであり、「これもまた過ぎ去る」ということをが分かります。
変化を恐れず柔軟に生きる―固定観念を手放す勇気
「自分はこうあるべきだ」という固定された自己観は、多くの束縛をもたらします。
固定観念を手放すことで、変化に柔軟に対応できるようになります。
大人になると、小さな変化には気づきにくくなりますが、子どもの成長を観察すると、「1ヶ月前の姿と今日の姿は異なる」という事実に直面します。
できるようになったことが徐々に増えていく成長を実感する中で、諸行無常という教えが示すすべてのものが常に変化し続けるという真理が、私たちに深い気づきをもたらしてくれます。
また、自己決定の力も大切です。
私たちは、自分自身の選択によって生き方を決める一方で、他者や環境との関係性によって大きな影響を受けています。
そのため、自己は孤立して存在するのではなく、常にご縁や相互依存の中で生まれ変わるものであり、固定されたものではないということを認識することが、自由な心を育む鍵となります。
まとめ
「本体なるものは存在しない」――これは、仏教の無常・無我・縁起の教えが示す真理です。
私たちが感じる「自分」とは、実は固定された実体ではなく、身体、感受、認識、形成、意識という五蘊の絶えず変化する集合体に過ぎません。
そして、自己は孤立した存在ではなく、家族や友人、社会とのご縁や関係性の中で常に再構成されるものです。
この真理に気づくことで、苦しみへの執着は薄れ、喜びをより深く味わうことができ、固定観念を手放す柔軟な心が育まれていくということです。