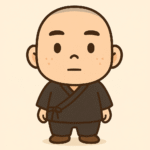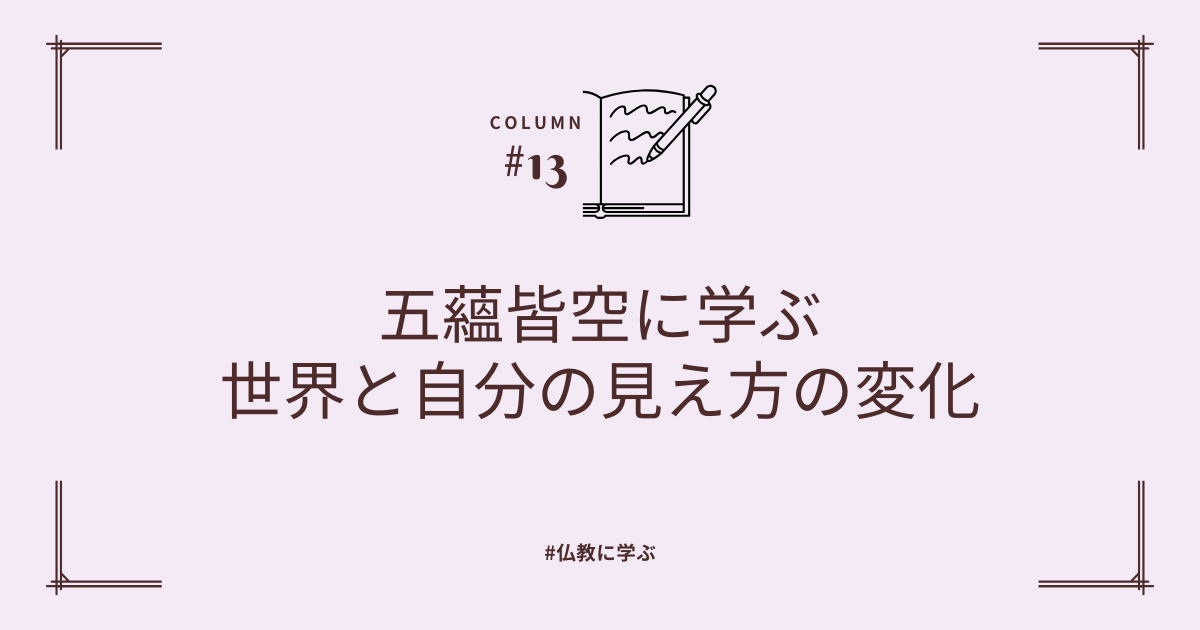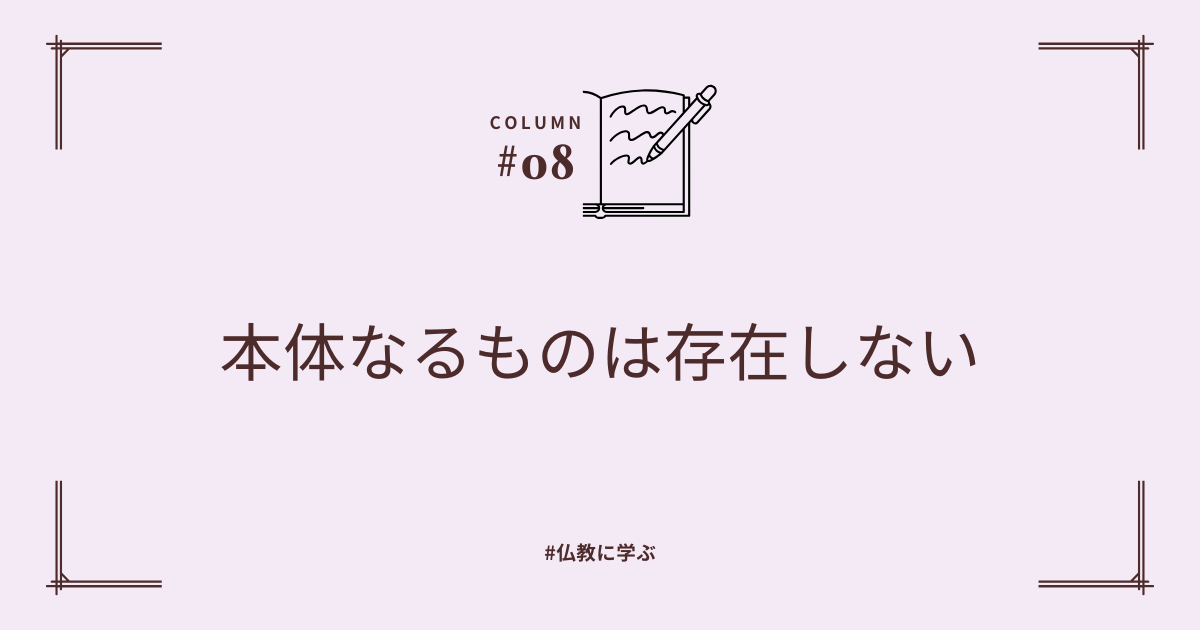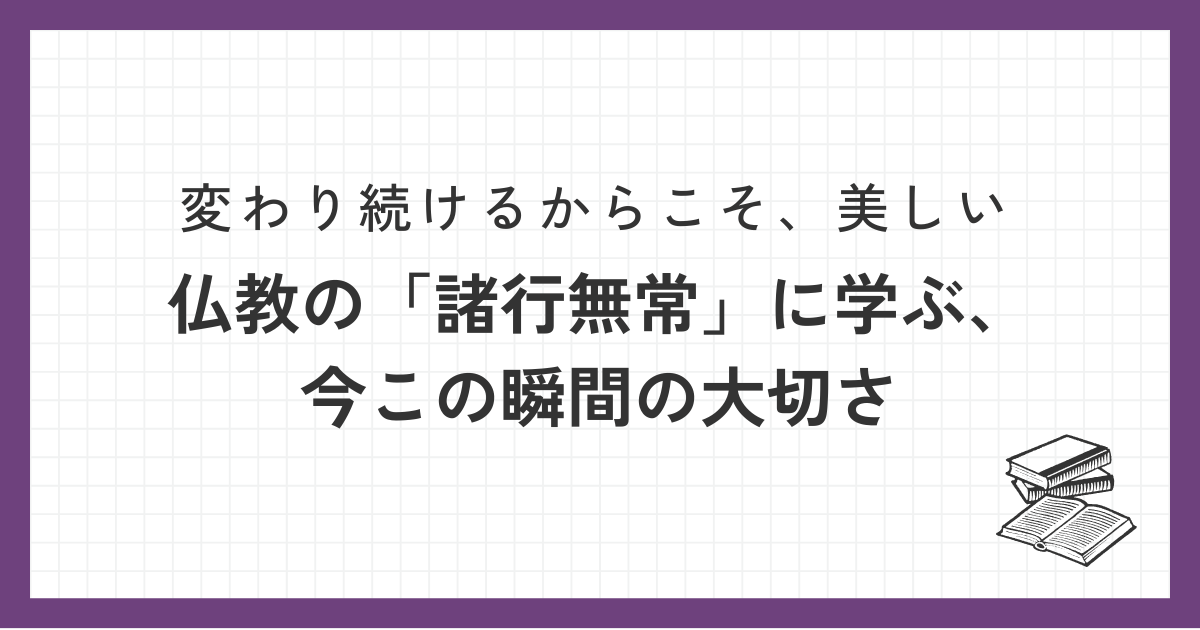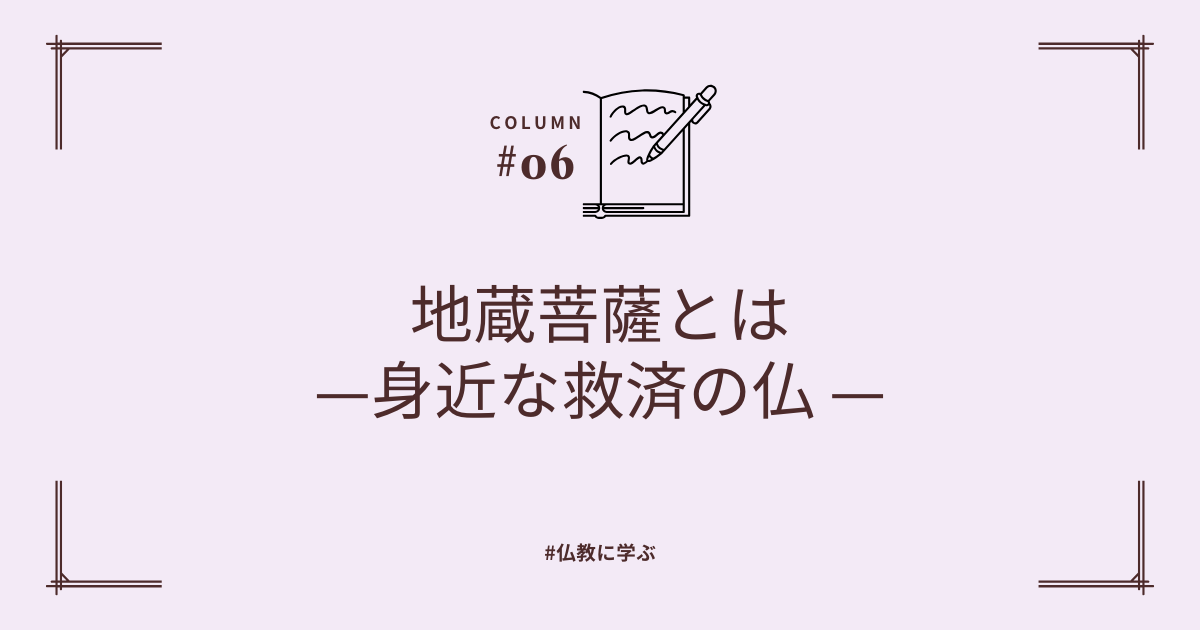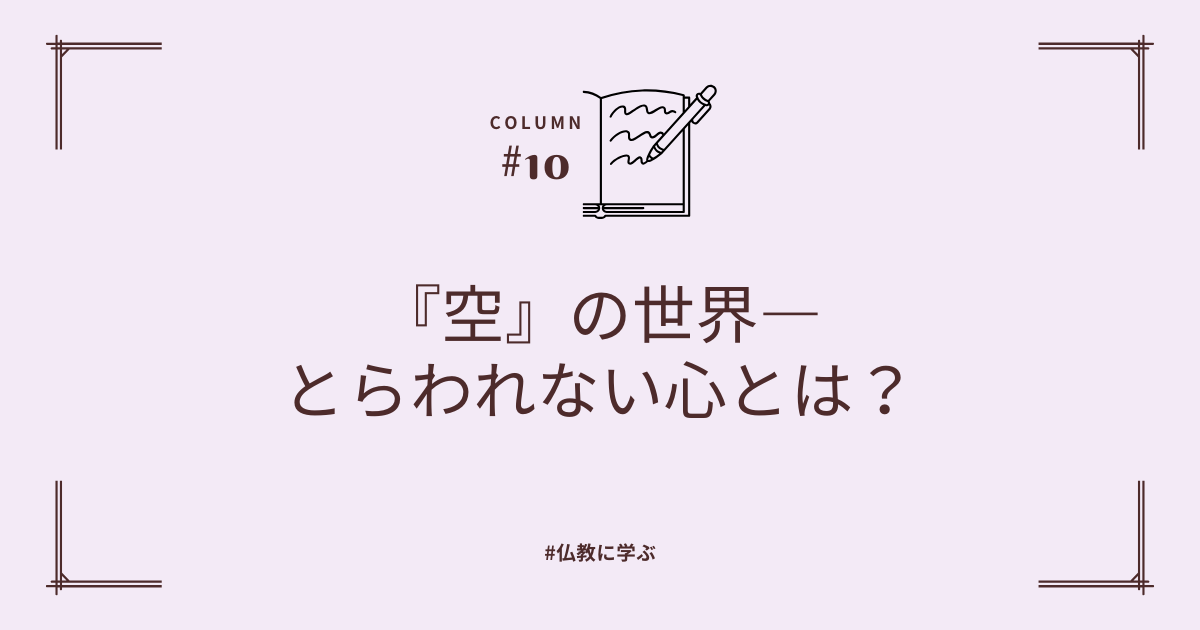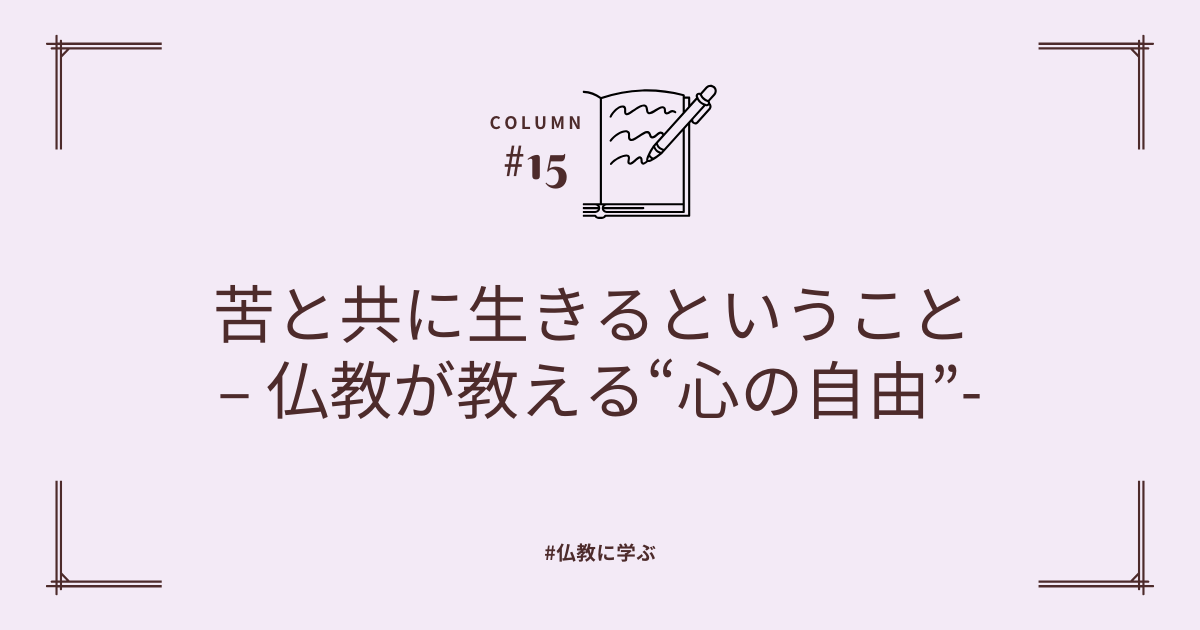変化に身をゆだねる -コロナ禍に学んだ無明と智慧 –
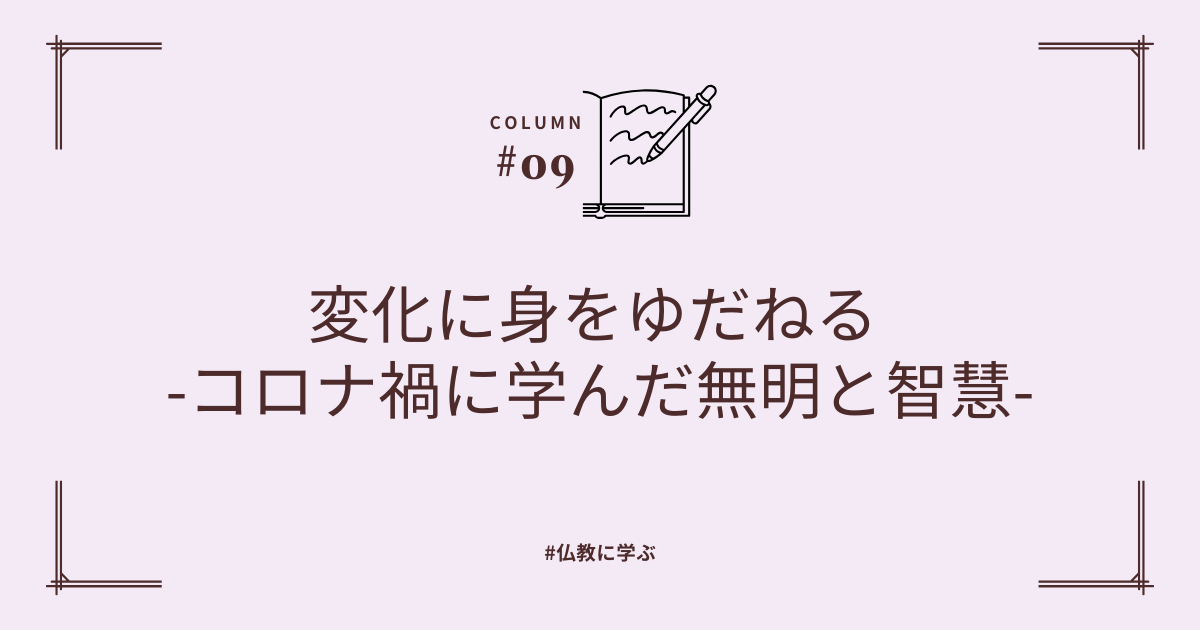
コロナ禍で、私たちの生活は大きく変わりました。
外出制限、リモートワークの増加、急速なデジタル化──。
私自身も、急な変化に対応しながら、心の中では「これまでと同じ生活をしたい」と思っていました。
現在は、コロナのピーク時とは異なり、以前の生活に近づいている部分もありますが、それでも完全に元通りではありません。
振り返ると、「変化に無理に適応しようとするから苦しいのでは?」と感じるようになりました。
この気づきを深めていくと、仏教の教えともつながっていることがわかりました。
苦しみの正体は「変化そのもの」ではなく「変化を拒んでいたこと」
コロナ禍で苦しんでいた理由を考えてみると、それは「変化そのもの」ではなく、「変化を拒んでいたこと」にあると気づきました。
緊急事態宣言が発令されると、外出が制限され、生活が一変しました。
同時に、リモート化やIT化が急速に進み、新しい生活様式に対応せざるを得ない状況になりました。
そんな中、私は「これまで通りの生活を続けたい」と強く思いながらも、「すぐに新しい生活に適応しなければ」と焦っていました。
しかし、思い通りにいかないことが増えれば増えるほど、苦しみは大きくなっていきました。
この苦しみの正体は、仏教でいう「無明」の状態だったのです。
仏教の視点で考える「無明」とは?
仏教では、「無明(むみょう)」とは、物事の本質を見失い、執着や思い込みによって苦しむ状態を指します。
この無明を離れられれば、苦しみから解放されると説かれています。
コロナ禍での苦しみも、仏教の「三法印(諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・一切皆苦)」を理解していないことから生じていました。
🔹 諸行無常(しょぎょうむじょう)
➡ 「すべては常に変化し続ける」 ➡ 「元の生活に戻りたい」と思っていても、すべては移り変わるもの。変化するのが自然なことだった。
🔹 諸法無我(しょほうむが)
➡ 「すべては固定されたものではない」 ➡ 「私はデジタルが苦手だから、ついていけない」と思い込んでいたが、人は環境とともに変化できる存在だった。
🔹 涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)
➡ 「煩悩から解放された安らかな境地」
➡ 変化を受け入れ、執着を手放すことで、心が静まり、安らかな気持ちで新しい日常に適応できるようになった。
🔹 一切皆苦(いっさいかいく)
➡ 「執着が苦しみを生む」 ➡ 「元の生活に戻らなければならない!」と執着することで、逆に苦しみが大きくなっていた。
つまり、変化を避けることはできないのに、それを受け入れようとせず、「変化に対応できない」と決めつけ、「元に戻らなければならない」と執着することが、コロナ禍をより苦しいものにしていたのです。
変化に身をゆだねると楽になる
ある日、車の中でラジオを聴いていると、こんな話を耳にしました。
「緊急事態宣言中、僕はとにかく読書していました。 自分で本を読もうと決めて、毎日読んでいたら、世の中が大変な渦中にあることすら感じなくなっていました。 無理に新しい生活様式に合わせようとすると大変だけど、いま自分ができることを選択すると楽ですよ。そのうち新しい生活にも慣れますから。」
そのときは何気なく聞いていましたが、後から振り返ると、このパーソナリティの話こそ、「変化に身をゆだねる」ということだったのだと気づきました。
急激な変化に適応しようと必死になっていたときは苦しかったですが、気づけば、新しい生活にも慣れ、デジタル化が進んだ世界も当たり前になっていました。
これは、「変化に抗わず、その中で自分にできることを見つけた」からこそ、自然と馴染んでいったのだと思います。
これからの変化をどう受け止めるか
コロナ禍だけでなく、これからもさまざまな変化が訪れます。
そのたびに、無理に適応しようと焦るのではなく、「自然と馴染んでいくもの」と理解すれば、もっと楽に生きられるのではないでしょうか。
✔ 「元に戻そう」とするのではなく、「新しい形を受け入れよう」と考える
✔ 「変化に逆らう」のではなく、「変化に身をゆだねる」
✔ 無理に何かを変えようとするのではなく、「今できること」に目を向ける
こうした考え方を持つことで、私たちはこれからの変化にも柔軟に対応できるようになります。
まとめ
コロナ禍での経験を通じて、私は「無理に適応しなくてもいい。時間とともに慣れる」と学びました。
変化を拒めば苦しくなるが、変化に身をゆだねれば、自然と新しい形が見えてくる
これからも変化は訪れるが、もう無理に適応しようとしなくていい
「変化に逆らわない生き方」を実践すると、もっと楽に生きられる
変化を恐れるのではなく、流れに身をゆだね、無理なく生きること。
私自身、これからもこの姿勢を大切にしていきたいと思います。